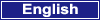201年09月24日
2-1 被害の概要
常総市上三坂地区の鬼怒川左岸(21k地点付近)において,越水破堤が発生した.破堤幅は,最終的には約200mとなっている.堤防の比高は約4mとされている.被害は,堤防のすぐ東側と堤防から約75m離れた道路の東側の住宅の流出である.流出した住家や倉庫などの構造物は約20棟となっている.堤防のすぐ東側での浸水深は約300㎝,堤防から約75m離れた道路付近では約100㎝であった.破堤箇所付近を除き浸水深度は低いが,流速が速いため落堀では約200㎝程度の洗掘を受けている.洗掘跡は,ガソリンスタンドの北側と南側にありそれぞれの幅は70m程度である.特に北側の洗掘跡は深く,東方の流下方向では白い住宅を挟んで2つに分流した.浸水深度は小さいが,最終的な落堀の深さから判断すると水深3m程度の速い流れが発生していたものと推定できる.構造物の流出は,堤防付近では破堤にともなう斜流と県道付近では県道を越えた際の斜流による構造物の基礎の洗掘により流出したものと推定できる.破堤部で流出を逃れた構造物は,ガソリンスタンドと鋼管杭で支持された基礎をもつ住宅のみであった.
2-2 防災上の課題
○“越水”に引き続く災害への危機感
鬼怒川の堤防は午前10時頃から堤防天端に迫っており,昼ごろに21k地点から越水している.堤防天端までの超過洪水→越水→破堤→洗掘による家屋の流出→洪水の拡散は,防災関係者であれば,これまでの河川破堤による災害で繰り返された現象であることは自明であるが,一般や行政担当者に対しての危機感が共有できなかった.天端までの超過洪水の時点で,堤防付近の住民の避難行動を開始すべきであったが,防災関係者と一般との危機感が乖離していることが繰り返される防災上(防災関係者)の課題である.これは,2004年の新潟県における7.13水害と同様な課題であり,新潟県において7.13水害以降に整備してきた行政・住民の防災体制を鬼怒川流域でも活用することが望まれる.
○洪水ハザードマップ等を利用した下流部での避難行動
若宮戸地区の越水と同様に,上三坂地区の破堤においても,多量の洪水の流入をもたらした.両地域から流入した洪水がより下流域へ拡散し,長期湛水が発生した.洪水ハザードマップ等を利用した下流部での避難行動が十分でなかったことが伺える.
(クリックで大きいサイズの画像が開きます)

図中の数字は,基準面(道路)からの浸水深度(cm).破堤部から流入した洪水は⑧地点付近まで洗掘跡を残している.砂堆は洗掘跡の両脇や流下方向の末端部に残されており,流入した洪水流が地形の低い部分に沿って東から南方へ流下したことがわかる.

浸水深度は100㎝程度と推定されるが,洗掘を含めると水深は200㎝程度となる.

破堤部東側の洗掘.右側の住宅は,北側(右側)が洗掘され傾いている.

道路部分も洗掘され流出している.

県道を越えた地点でも斜流による洗掘が発生している.洗掘部分には住宅があった.


重量鉄骨構造の住宅付近の様子.住宅の基礎は約1mピッチで施工された鋼管杭で支持されており,流下してきた住宅2棟を受け止めていた.基礎部は洗掘されている.この場所では合計6名+犬2匹が救助されている.

破堤した堤防付近にあった住宅の2階部分.落堀に沿って流下した.

落堀の流下方向に広がる砂堆.厚さは40㎝程度で2つのユニットに区分できる.